特色のある委員会活動
教育委員会(2022年度実施分)
全職員を対象とした教育や研修プランを立案し実施しています。
- リフレッシュ研修(新規入職者対象・2回/年)
- 湯野ウォークラリー及びフォトコンテスト
- 「キンボール」スポーツレクリエーション
- 全体研修(1回/月)
- 他部署研修【シャドイング】
- 5sポスター発表
CFT委員会
当院におけるCFT(クロスファンクショナルチーム)は、各病棟(回復期・障害者一般)における課題解決のために、全部署横断的に選抜されたメンバーで構成されています。
医療安全(転倒予防チーム)
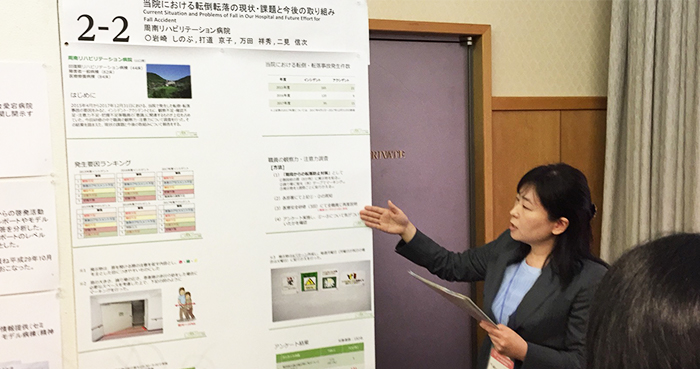
医療に関わるあらゆる種類の危険を認識し、医療安全のための対策および職員教育を行うとともに、事故発生時およびその後の対応を行うための委員会です。年に2回の全職員を対象とした研修や院内ラウンド等を行っています。
また、当院は、日本転倒予防学会に施設会員登録しており、PT1名、看護師2名が転倒予防指導士として認定されています。院内での研修、転倒予防に関する啓発活動や地域の高齢者に対する体操指導等行っています。
地域支援活動委員会

地域包括ケアシステムの構築に向け、専門職の在り方も問われる時代の中、当院では平成29年度より、地域支援活動委員会を立ちあげ、有償・無償に関わらず、プロボノ活動を積極的に行っています。
院内感染防止対策委員会
病院内における院内感染症の発生を未然に防止するとともに感染症が発生した場合には迅速かつ適切な対応を行うための委員会です。
年に2回の全職員を対象とした啓蒙研修や院内ラウンドを行なっています。
又、その結果をフィードバックする事により更に感染対策に関する知識を高め重要性を自覚するように導いています。
褥瘡対策委員会
日本褥瘡学会施設会員に登録し、委員会では多職種による医師、看護師、栄養士、セラピスト、薬剤師、事務職員で構成されています。毎月1回褥瘡回診、委員会を行っています。発生予防を重視しドレッシング剤、体圧分散マットレスも豊富に揃えています。これから予防に力を入れていきたいと思います。
褥瘡対策チーム委員会
各病棟ごとに褥瘡患者の新規発生、継続患者の報告を行い対策を検討しています。
褥瘡の評価、治療内容の検討、体圧分散寝具の指導を行っています。
NST委員会
平成30年度より口腔ケアサポート委員会を融合して新たに再編成 栄養管理、口腔内管理、摂食嚥下・リハビリテーションを柱とし活動しています。
臨床倫理委員会
臨床現場における様々な倫理的課題に対するコンサルティング、また倫理的課題に気づき、対応できる職員の育成、研究発表等に関する倫理的審査を主に行っています。
また、日本臨床倫理学会の施設団体会員であり、現在、臨床倫理認定士養成研修に、看護師とリハスタッフが参加しています。
